今週は米国・日本・欧州の金融政策と市場の反応が主役でした。米連邦公開市場委員会(FOMC)は6会合ぶりに政策金利を0.25%引き下げ、誘導目標レンジを4.00〜4.25%とした(出典:dir.co.jp)。公表されたドットチャートでは年内にさらに0.50ポイントの追加利下げが示され、2026年以降は緩やかな利下げペースが想定されています(出典:dir.co.jp)。雇用環境の悪化と関税によるインフレ懸念が背景にあり、市場は今後の利下げのタイミングを慎重に見極めています。
日本では、日銀が保有するETF・J-REITの市場売却を始めるという歴史的な方針転換を発表し、保有残高約37.2兆円のETFなどの売却完了には100年以上かかる見通しと報じられました(出典:dir.co.jp)。金融政策委員会では2名が利上げを提案し、長期国債利回りは一時17年ぶりに1.665%まで上昇しました(出典:jp.reuters.com)。一方で東京株式市場は円安と景気期待を追い風に連日最高値を更新し、日経平均は45,754.93円で取引を終えました(出典:jp.reuters.com)。
欧州では欧州中央銀行(ECB)が公表したデータで、8月のユーロ圏企業向け融資が前年比3.0%増と伸びを加速させ、家計向け融資も2.5%増に加速したことが分かりました(出典:jp.reuters.com)。金利低下が融資の追い風となっており、ECBの過去1年の200ベーシスポイントの利下げ効果が現れています(出典:jp.reuters.com)。
それでは個別のニュースを見てみましょう。
FOMCが0.25ポイントの利下げを決定
ニュース概要
9月16〜17日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で、政策金利(FF金利誘導目標レンジ)が4.25–4.50%から4.00–4.25%へ0.25ポイント引き下げられた(出典:dir.co.jp)。ドットチャートの中央値では年内残り二回の会合で合計0.50ポイントの追加利下げが示され、2026~27年は各年0.25ポイントずつ利下げが見込まれている(出典:dir.co.jp)。
ニュース解説
FOMCが約半年ぶりに利下げに踏み切った背景には、米国の雇用環境の悪化と関税の影響によるインフレリスクがあるとされます(出典:dir.co.jp)。市場は今回の利下げを織り込んでいたためサプライズはなかったものの、今後の利下げペースについては参加者間で意見が分かれています。ドットチャートに示された2026年以降の利下げペースが緩やかなのは、当局が中期的には景気・雇用の改善やインフレ率の再上昇を予想しているためです(出典:dir.co.jp)。利下げ観測が市場の期待より鈍化すれば、債券や株式市場の調整につながる可能性があります。
キーワード
- FF金利 … 米国の銀行間で短期資金を取引する際の金利で、FRBが金融政策の指標とする。
- ドットチャート … FOMC参加者が将来の適切な政策金利見通しを示す図。各年の利上げ・利下げの想定幅が読み取れる。
ニュースソース
(出典:dir.co.jp)
米国債利回りが上昇、次回の利下げ見通しに慎重姿勢
ニュース概要
FOMC後の米国債市場では長期金利が上昇し、10年国債利回りは4.142%と2.3ベーシスポイント上昇した(出典:jp.reuters.com)。2年債利回りは3.605%まで上昇し、一時3週間ぶりの高水準となった(出典:jp.reuters.com)。市場は10月FOMCで0.25ポイントの利下げを行う確率を約90%と織り込んでいる(出典:jp.reuters.com)。
ニュース解説
利下げ後も米長期金利が上昇したのは、FRBが追加利下げに慎重な姿勢を示し、経済指標が底堅かったためです。10年国債利回りの上昇は住宅ローンや企業借入の金利上昇を通じて景気に下押し圧力をかける一方、短期金利との格差縮小は利ざやの薄い銀行にとっては悪材料です。市場では10月会合での利下げはほぼ織り込み済みですが、今後の経済指標次第で見通しが変わる可能性があります。
キーワード
- ベーシスポイント(bp) … 金利の単位で、1bp = 0.01%。
- 利回り格差 … 2年債と10年債など異なる期間の国債利回りの差。景気や金融政策の期待を反映する。
ニュースソース
(出典:jp.reuters.com)
シティが金価格見通しを1オンス=3,800ドルに引き上げ
ニュース概要
シティ(Citigroup)は19日、金価格の予想を1オンス=3,800ドルに引き上げ、従来の予想3,600ドルから200ドル上方修正した(出典:jp.reuters.com)。米労働市場の軟化や関税による経済成長への懸念が循環的な上昇要因とされ、米財政赤字やドルの地位に対する不安、FRBの独立性への懸念などが構造的な要因として挙げられている(出典:jp.reuters.com)。
ニュース解説
金はインフレや金融不安のヘッジとして買われる傾向がある。シティは基本シナリオとして数カ月以内に金価格が3,800ドルの史上最高値に到達し、2026年第1四半期にピークを迎えると予想する(出典:jp.reuters.com)。米国がスタグフレーションや景気後退に直面した場合には金が4,000ドルまで上昇する可能性もあると指摘する一方、関税交渉が進展し米経済が持ちこたえれば3,400ドルまで下落する可能性も示された(出典:jp.reuters.com)。金価格の上振れ・下振れは国際資本の動きに影響し、為替や株式市場にも波及する。
キーワード
- スタグフレーション … 経済成長の停滞とインフレの同時進行。
- ドルの地位 … 国際決済通貨としての信認度。財政赤字や金融政策によって変動する。
ニュースソース
(出典:jp.reuters.com)
日銀がETF・J‑REITの超長期売却を決定
ニュース概要
日銀は9月19日の金融政策決定会合で、保有するETFとJ‑REITを市場で段階的に売却する方針を決定した。保有残高はETFが簿価約37.1861兆円、J‑REITが6,550億円にのぼり、売却完了には100年以上かかると見込まれている(出典:dir.co.jp)。
ニュース解説
リーマンショック後に株価下支え目的で積み上げた巨額のETFを市場で処分するのは日銀にとって大きな政策転換です。保有資産が巨額なため、売却はゆっくり行い市場への影響を抑える方針で、金融市場が不安定になればペースを遅らせる可能性も示唆されています(出典:dir.co.jp)。一方で、株価下落局面では評価損が膨らみ国庫納付金が減少する恐れがあり、将来の損失に備えて引当金を積むべきだとの提言もあります(出典:dir.co.jp)。超長期にわたる売却は、中央銀行が市場に介入した政策の出口戦略として注目されます。
キーワード
- ETF(上場投資信託) … 株価指数などに連動する金融商品で、証券取引所で売買できる。
- J‑REIT … 不動産投資信託。賃貸収入や不動産売却益を配当に回す仕組み。
ニュースソース
(出典:dir.co.jp)
長期国債利回りが17年ぶりの高水準に
ニュース概要
9月22日の国債市場では、10年物国債利回りが一時1.665%と2008年7月以来の高水準になり、2年債利回りも0.930%に上昇した(出典:jp.reuters.com)。日銀金融政策決定会合で委員2人が利上げを提案し、早期の利上げ観測が強まったことが背景にある(出典:jp.reuters.com)。
ニュース解説
利上げ観測と米長期金利の上昇が重なり、国債先物は続落しました。日本の長期金利が1%台後半まで上昇したのは金融危機前以来で、債券価格の下落を意味します。国債利回りの上昇は住宅ローン金利や企業の資金調達コストの増加につながり、景気に影響を与える可能性があります。日銀が将来的に政策金利を引き上げる姿勢を示しているかどうか、次回会合が注目されます。
キーワード
- 国債先物 … 国債を将来の期日に現在の価格で売買する先物取引。金利動向を反映する。
- 利上げ観測 … 投資家が中央銀行の将来的な利上げを予想すること。
ニュースソース
(出典:jp.reuters.com)
日経平均が終値ベースで史上最高値を更新
ニュース概要
9月25日の東京株式市場で日経平均は124円62銭高の45,754.93円となり、終値ベースで史上最高値を更新した(出典:jp.reuters.com)。円安基調や投資家の先高観が支えとなり、TOPIXも0.47%高の3,185.35ポイントと最高値を記録した(出典:jp.reuters.com)。
ニュース解説
円安が輸出企業の業績改善期待につながり、半導体や商社など幅広い業種に買いが入りました。また、日銀が市場介入から出口戦略へと移行する中で金融株への関心も高まりました。9月期末の配当権利取り最終日にもかかわらず株価が堅調だったことから、投資家が短期的な権利落ちよりも長期的な株高を意識していることがうかがえます(出典:jp.reuters.com)。一方で高値警戒感から利益確定売りも出ており、今後の調整局面への注意も必要です。
キーワード
- 権利付き最終日 … 配当や株主優待を受け取るために株を保有すべき最終日のこと。
- TOPIX … 東証プライム市場全体の株価動向を示す指数。
ニュースソース
(出典:jp.reuters.com)
米NY市場サマリー:PCE物価指数上昇でドル高続く
ニュース概要
9月26日のNY市場では、8月の米個人消費支出(PCE)物価指数が前年比2.7%上昇し、前月から伸びが加速したことが判明した(出典:jp.reuters.com)。ドル/円は取引終盤に149.48円前後で推移し、ドル指数は週足で2週連続の上昇となる見通し(出典:jp.reuters.com)。CMEのフェドウオッチでは10月FOMCでの利下げ確率が約89.8%に低下した(出典:jp.reuters.com)。
ニュース解説
PCE物価指数はFRBがインフレ指標として注目する統計で、インフレが鈍化していないことが確認されたため米国債利回りが上昇しました。これによりドル買いが進み、ドル/円は150円に迫る水準で推移しました(出典:jp.reuters.com)。FRB高官は雇用とインフレのバランスを取る必要性を強調し、バーキン総裁は追加利下げを慎重に検討する姿勢を示す一方、ボウマン副議長は雇用市場の混乱を避けるためには断固とした利下げが必要だと発言しました(出典:jp.reuters.com)。市場は利下げペースに対する見方を微調整しており、今後の指標次第でドルや債券利回りの動きが変わるでしょう。
キーワード
- PCE物価指数 … 個人消費に基づく物価指数で、FRBがインフレ指標として重視する。
- フェドウオッチ … シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)が提供する、FOMCの利上げ・利下げ確率を示すデータ。
ニュースソース
(出典:jp.reuters.com)
M&A市場に楽観論、産業再編とPE主導案件が後押し
ニュース概要
ゴールドマン・サックスのジョン・ウォルドロン社長はニューヨークで行われた会合で、さまざまな産業部門の再編やプライベート・エクイティ(PE)主導の案件加速によってM&Aの見通しがこれまで以上に楽観的になっていると述べた(出典:jp.reuters.com)。FRBの利下げは企業の資本コストを下げ、M&Aをさらに促進すると指摘した(出典:jp.reuters.com)。
ニュース解説
近年停滞していたM&A市場が再び動き始めています。鉄道業界での大型買収案件に触れたウォルドロン氏は、他業界でも同様の動きが出てくると予想しており、PEファンドによる買収案件が増加していると述べました(出典:jp.reuters.com)。低金利環境が続けば企業が手元資金や借入を活用しやすくなり、大型買収や業界再編が進む可能性があります。M&Aの活性化は銀行や投資銀行の収益拡大に寄与するとともに、投資家にとっても新たな投資機会を生み出します。
キーワード
- プライベート・エクイティ(PE) … 未公開企業への投資を専門とするファンド。企業の買収や再編を行い、価値向上後に売却益を得る。
- 資本コスト … 企業が資金調達を行う際に必要となるコスト。金利低下により下がる。
ニュースソース
(出典:jp.reuters.com)
ヘッジファンドが銀行・保険株を積極購入
ニュース概要
ゴールドマン・サックスのリサーチによると、ヘッジファンドは先週、銀行・保険・消費者金融株を過去3カ月で最も速いペースで購入した(出典:jp.reuters.com)。欧州の銀行株指数は年初来40%超上昇し、米国の銀行株指数も20%強上昇している(出典:jp.reuters.com)。ヘッジファンドのグロスレバレッジも過去8カ月で最大の上昇を記録した(出典:jp.reuters.com)。
ニュース解説
金利上昇局面では銀行の利ざや拡大が期待できるため、利上げ観測やM&A活発化の動きが金融株への資金流入につながっているとみられます。欧米の銀行株が大きく上昇している背景には、規制緩和や業界再編への期待もあります。ヘッジファンドが金融株を多く買い付けることは、市場全体のリスク許容度が高まっているサインとも取れますが、過度のレバレッジは相場の変動要因にもなり得るため注意が必要です。
キーワード
- ヘッジファンド … 高いリターンを狙い、多様な投資手法を用いて運用する投資ファンド。
- グロスレバレッジ … 資産総額に対する借入などの倍率。高いほどリスクが大きい。
ニュースソース
(出典:jp.reuters.com)
ユーロ圏の銀行融資が加速、ECB利下げの効果
ニュース概要
欧州中央銀行(ECB)のデータによると、8月のユーロ圏企業向け銀行融資は前年比3.0%増となり、前月の2.8%から伸びが加速した(出典:jp.reuters.com)。家計向け融資も2.5%増と、2023年4月以来の高水準に上昇した(出典:jp.reuters.com)。ECBは過去1年で200ベーシスポイントの利下げを実施しており、それが融資拡大を後押ししている(出典:jp.reuters.com)。
ニュース解説
ユーロ圏では景気低迷を背景にECBが積極的に利下げを行い、企業や家庭が低金利で資金調達しやすくなっています。融資の増加は設備投資や住宅購入を刺激し、経済成長の下支えとなります。一方で、マネーサプライM3の伸び率は2.9%と予想を下回り、ECBのバランスシート縮小が資金供給を抑えていることも示されました(出典:jp.reuters.com)。過度な融資拡大は不良債権の増加を招くため、金融機関のリスク管理が重要です。
キーワード
- M3 … 現金や預金など広義のマネーサプライ。経済全体の資金量を示す指標。
- 利下げ … 中央銀行が政策金利を引き下げること。融資促進や景気刺激を目的とする。
ニュースソース
(出典:jp.reuters.com)
暗号資産市場が軟調、主要コインが下落
ニュース概要
9月26日9時時点の暗号資産市場では、時価総額が580.34兆円、24時間の売買代金が23.30兆円だった(出典:cc.minkabu.jp)。主要通貨ではビットコインが16,356,928円(-3.05%)、イーサリアムが582,797円(-5.77%)、XRPが412.176円(-5.54%)と下落した(出典:cc.minkabu.jp)。時価総額100億円以上の53銘柄のうち、上昇は4銘柄、下落は48銘柄だった(出典:cc.minkabu.jp)。
ニュース解説
米国の経済指標が予想を上回ったことから利下げ期待が後退し、暗号資産市場はリスク資産売りの影響を受けています。ビットコインなどの価格は昨年から大きく上昇していましたが、高値圏では利益確定売りも出やすく、価格変動が大きくなっています。過去7日ではパレットトークンが+5.78%、過去30日ではアバランチが+20.26%と上昇した一方、ユニスワップが-21.24%、クアンタムが-29.05%と下落しています(出典:cc.minkabu.jp)。投資家は各銘柄の用途やリスクを理解したうえで慎重に取引する必要があります。
キーワード
- 時価総額 … 発行済み暗号資産の総額を価格で換算したもの。市場規模の目安。
- アルトコイン … ビットコイン以外の暗号資産の総称。用途や技術が多様で値動きも幅広い。
ニュースソース
(出典:cc.minkabu.jp)
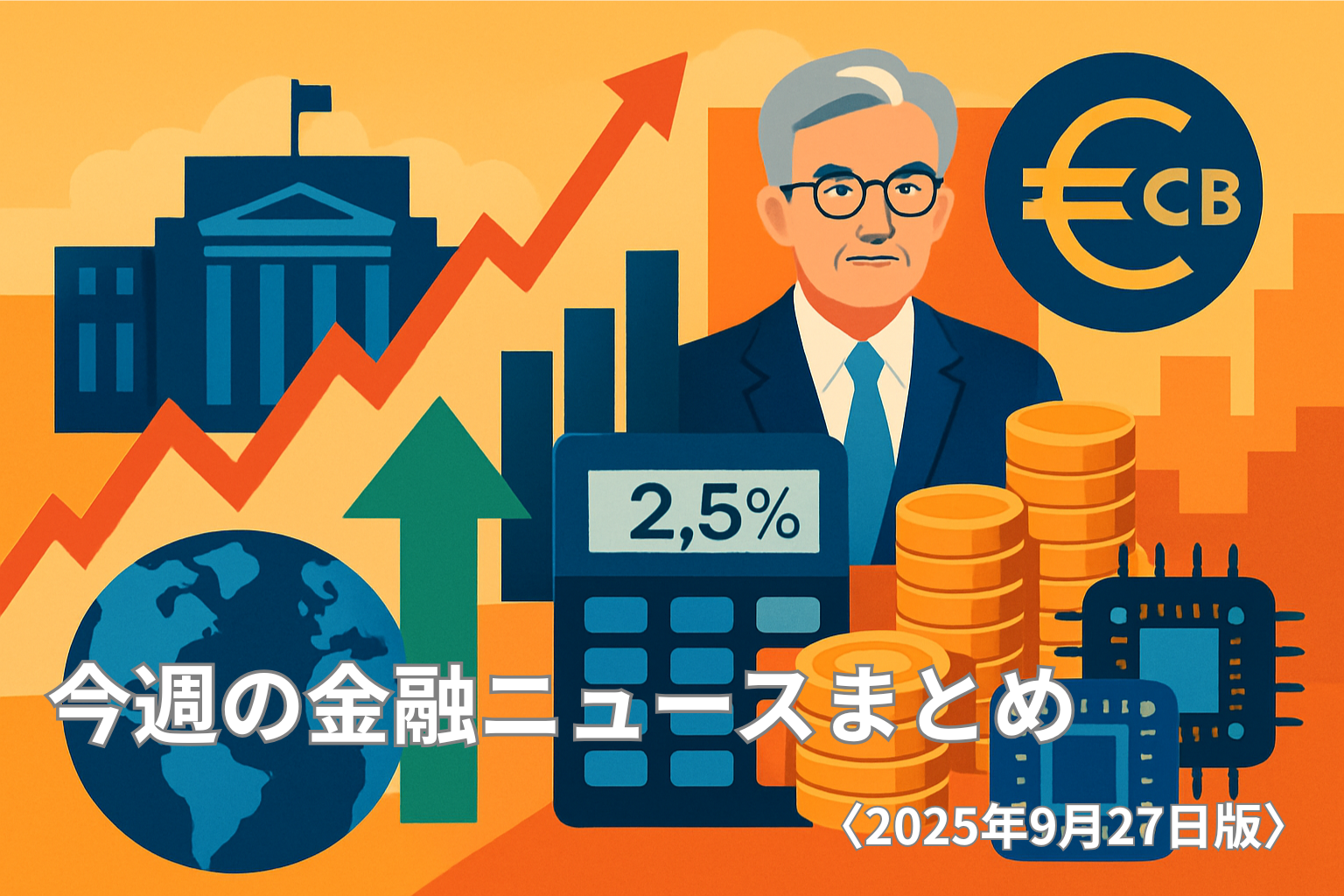


コメント